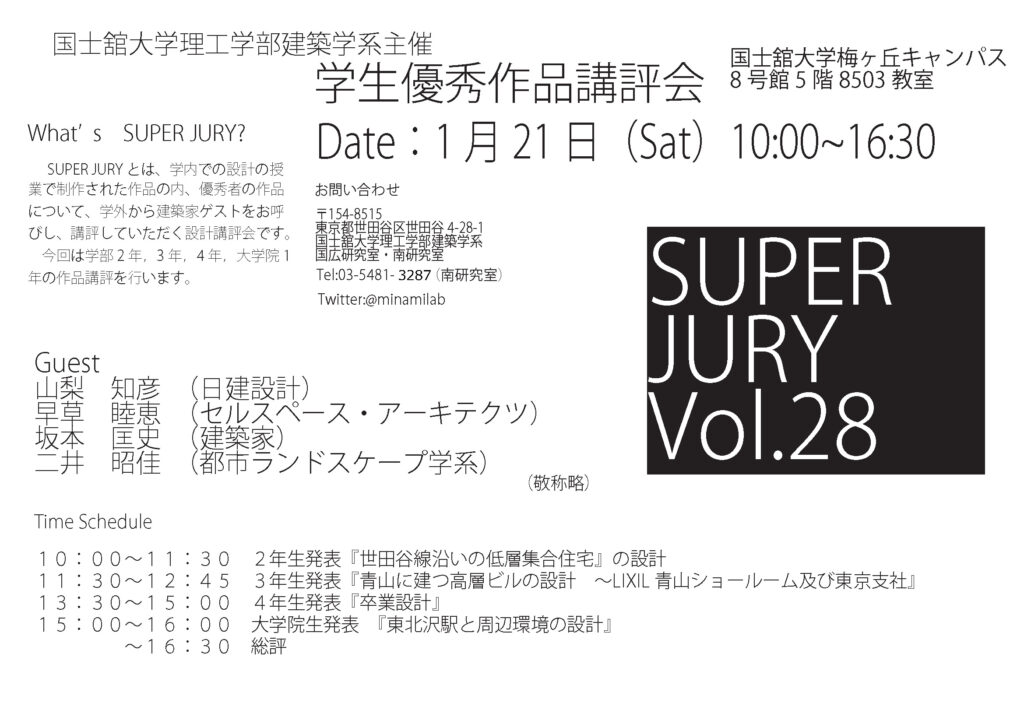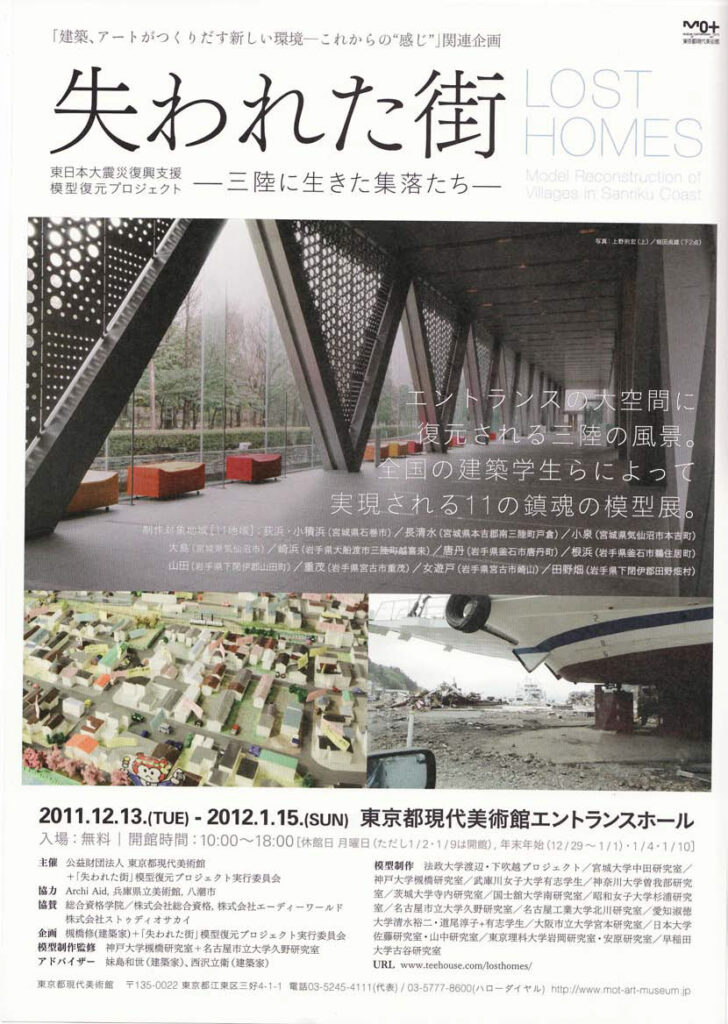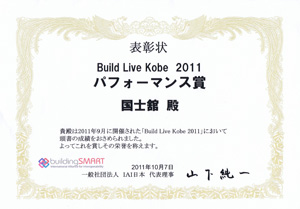本学大学院建設工学専攻M1の都築和義さん
タイでのワークショップ参加時撮影した写真が10+1 web siteに掲載されました。
PHOTO ARCHIVES の【137 タイ】のページです。(見当たらない場合は、バックナンバーを参照して下さい。)
(10+1 web site:都市/建築に関する展覧会、イベントなどを紹介するサイト)
SuperJury28 開催のお知らせ
2012年1月21日(土曜日) 9:30~17:00 8号館8503教室及び製図室(又は建築スタジオ)
ゲスト審査員:
山梨和彦さん〈日建設計〉
早草 睦惠さん〈セルスペース・アーキテクツ〉
坂本匡史さん〈建築家〉
二井昭佳さん〈本学都市ランドスケープ学系〉
発表方式変更:ポスターセッション形式。全員がノミネートされ、優秀作品に投票。上位4~5名の発表。
9:30~ 全体の流れ、課題説明
10:00~11:30 2年生対象
11:30~12:45 3年生対象
12:45~13:30 昼食
13:30~15:00 4年生 、全員発表
15:00~16:00 大学院生
卒業研究梗概 テンプレート
卒業研究提出用梗概のテンプレートは、下記よりダウンロードして下さい。
また、書き方については、「卒業研究梗概の書き方」を参考にして下さい。
卒業論文テンプレート(Zipファイルです。Windows7では、IEで自動的に解凍され、使用可能となります。)
卒業研究梗概の書き方(pdf)
学生設計作品展(LIXIL)のお知らせ
「LIXIL青山ショールームビルを設計し、提案せよ」
という仮想の課題のもとで生まれた学生設計案を、LIXIL:GINZAの展示スペースにて紹介する展覧会。
開催期間 2012年1月12日~1月19日
開館時間 10:00~18:00(土・日は休館)
場所 LIXIL:GINZA 7階クリエイティブスペース
入場無料
「(仮想)LIXIL青山ショールームビルの提案」詳細
建報社 HPの紹介記事
LIXIL 青山ショールームビルの提案/ポスター
東京都現代美術館、「失われた街-三陸に生きた集落たち」展
東京都現代美術館において、現在開催中の「建築、アートがつくりだす新しい環境-これからの“感じ”」展の関連企画として、美術館エントランスホールで『失われた街 −三陸に生きた集落たち−』と題した展示を行います。
会 期: 2011年12月13日(火)〜2012年1月15日(日)
会 場: 東京都現代美術館 エントランスホール
観覧料:無料
この展示に、南研究室も模型制作で協力し、6モジュールを制作、展示致しますので機会がありましたご覧下さい。
詳しくは、・東京都現代美術館HP
・展示詳細をご覧下さい。
前田圭介さんが新建築「住宅特集」に寄稿しました。
本学建築学系を1998年に卒業され広島在住の建築家、前田圭介さんが「住宅特集」2011年12月号の「コラム&エッセイ」欄に寄稿しました。同誌の9月号で紹介されたスタジオ兼住居の「Wishing
Well」を訪れてレポートしています。
大竹博氏講演会報告
日時:2011年11月22日(火曜日) 13:00~16:00
場所:国士舘大学梅ヶ丘校舎34号館B304教室
講師:大竹博氏
「福祉のまちづくり」、「福祉住環境論」の授業の一環として、講演会が開催されました。
50名ほどの参加者と質疑応答を交えながら、若干規定時間をオーバー。視覚障害当事者である大竹氏を取り巻く生活環境について、日々思うこと、など貴重なお話を窺うことができました。特に、大竹氏は途中失明という経緯から、学生から「光を失って自暴自棄にならなかったのか」「どのようにして前向きで建設的に取り組めるようになったのか」など、心理的な側面に対しての質問も相次ぎました。今後は、もう少し実践的なことに展開できたらと考えております。(福祉住環境論:田中千歳先生報告)
大竹博氏講演会のご案内
日時:2011年11月22日(火曜日) 13:00~16:00
場所:国士舘大学梅ヶ丘校舎34号館B304教室
講師:大竹博氏
世田谷区梅丘在住。33歳在職中糖尿病合併症により全盲となる。
・世田谷区視力障害者福祉協会副理事長
・東京都盲人福祉協会世田谷支部長城南ブロック長
・世田谷区UD審議会委員
他を歴任。
「福祉のまちづくり」、「福祉住環境論」の授業の一環として、講演会を開催します。
せっかくの機会ですので、授業を受講している学生以外の学生や一般の方にも開放致します。
学生証を持っていない方は、事前にメールをいただければ幸いです。
メールアドレスや、その他詳細事項は、pdfを展開後、ご確認下さい。